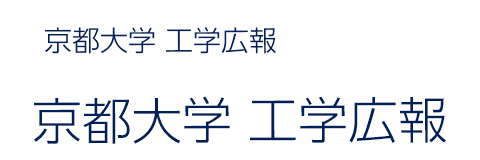コミュニケーションの難しさ
副研究科長 蓮尾昌裕
 はじめに
はじめに
本年4月から副研究科長を拝命し,教育を担当させていただいております。また時を同じく桂図書館長も拝命しました。教育も図書館も,教員はもとより学生の日々にとってとても大切なものです。これまで工学研究科執行部の経験がないこともあり,日々重責を感じながら,立川研究科長はじめ研究科長・副研究科長と教職員の皆様の力に支えていただき,なんとか職務を進めている状況です。どうか引き続き,よろしくお願いいたします。
ところで令和2年10月1日より,大学本部で研究公正担当の理事補を務めています。その用務の中に本部からの情報発信に関わることが含まれており,一方この4月からは,その情報を部局執行部の立場として受け取ることになりました。情報発信の際には,いかに各研究室の現場隅々まで届けるかに腐心していたのですが,いざ各学科・専攻に情報をつなぐ立場となって,ますますその難しさを強く実感しているところです。本稿では研究公正を一例に,過去の経緯を振り返りつつ,コミュニケーションの難しさについて所感をまとめます。風通しの良いコミュニケーション醸成の一助になればと思います。
これまでの振り返り
令和2年11月30日に文科省から,「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく令和2年度機動調査の実施について京都大学に通知されました。ざっくりと要約しますと
・旅費や謝金に関する不正及び「研究者の倫理観や規範尊寿意識の欠如」に対しては,再発防止策にどのように取り組んでいたのか
・研究費不正事案の発生要因と,それぞれの発生要因に対して新たに講じた再発防止策の内容と具体的なロードマップの提示
等への回答が求められました。
機動調査の結果として,令和3年3月26日に「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づく令和2年度機動調査の結果及びフォローアップ調査の実施についての通知があり,そこでは
・不正事案が頻発している事態については,表面的な分析のみで対策も外形的なものにとどまっていた
・教職員に対してどの程度意識が浸透しているのかが明らかでなかった
等の所見のもと,残念ながら以下の管理条件を付与され,文科省によるフォローアップ調査が実施されることになりました。
・京都大学において繰り返し不正が発生している要因を分析・評価し,リスクマネジメントを行うとともに,本部,部局の果たす役割を明確化して不正防止計画に反映すること
・不正を起こさせない組織風土を形成するため,コンプライアンス教育及び啓発活動を体系的に評価・整理し,教職員の意識改革に資する実効性のある取組として実施すること
・最高管理責任者は内部監査部門及び監事との連携を強化して,組織的牽制機能の充実に取り組むこと
・再発防止策には,具体的な指標を設け取り組むこと
履行期限を令和4年3月25日とされ,履行が認められないと間接経費措置額が削減されるという瀬戸際に追い込まれ,大学全体が危機感に包まれました。
その後,旅費のシステム変更や監査の厳格化,e-ラーニング研修の抜本的見直しとアンケート調査の実施等,大きな変化を実感されたことと思います。皆様のご協力もあって,
・今後も不正防止対策実施本部の各種取り組みを確実に継続することにより,「不正を起こさせない組織風土の形成」のため「教職員の意識改革」を進めることが求められる
との所見のもと,令和4年3月31日の通知により文科省から管理条件が解除され,フォローアップ調査が終了することとなりました。
このような制度変更や取組みとともに,教職員の意識改革促進のために研究公正担当理事による部局キャラバンも実施されることになりました。昨年度の部局キャラバンでは,部局執行部と意見交換するだけではなく,執行部がおられない場で若手研究者や秘書の方との意見交換も行いました。このような場では,負担増は仕方がないにしても,なぜその制度変更が必要なのかの説明が足りないとの意見もいただきます。確かに,理解できる理由があれば,負担感が軽減され,変化を前向きにとらえていただける可能性は高くなります。実際,キャラバンの実施報告書でも
・隅々まで行き渡る,途中で目詰まりを起こさないコミュニケーションの必要性
・職員と教員,職員間の敷居を下げるコミュニケーションの必要性
・ルールのばらつきを誘起する事務内の情報共有不足や教員への説明不足に対する工夫の必要性
を課題として挙げています。
部局におけるコミュニケーションの難しさ
4月からの工学部・工学研究科の会議で研究公正に関する議事がいくつかありました。例えば,5月の専攻長会議では「公正な研究活動の推進と研究費等の適正な使用について」の議事があり,事務方からかなりの熱量をもって本稿でこれまでまとめた経緯の主要部分が説明され,約20ページもの資料を使って,e-ラーニング研修等,今年度も気を緩めずに取り組んでほしい旨の報告がありました。
専攻長はこれまでの経緯もご存じであり,会議では内容もその理由も十分に伝わったと思いますが,100ページを超える会議全体の資料の中,各専攻に持ち帰って説明される際にどこまで伝えるべきか悩まれたのではないかと思います。管理条件が解除されて丸2年が過ぎ,危機感が薄れるとともに,当時を知らない教員・研究者・学生も増えています。
特に工学研究科では,専攻長会議を受けて,各専攻で専攻構成員への伝達の会議があり,さらに内容によっては各研究室での伝達へと進みます。そのために伝言ゲームとなり,各研究室の現場隅々までは真意が伝わらない可能性があります。部局キャラバンでは,専攻サイズ程度の小さな部局でも若手の教員・研究者や学生への情報伝達の難しさを課題とされており,一堂に会する機会を設けて,コミュニケーションの困難を克服されようとする試みも聞きました。一方,大組織である工学研究科ではそのような試みは現実的ではなく,より大きな難しさを抱えています。
また,e-ラーニング研修の受講依頼等はメールにて事務的に構成員に直接送られますが,日々届く多数のメールやe-ラーニング研修受講依頼の中で,負担感以上の意味を読み取ってもらうことは大変難しいようです。また,説明の文章量が多くなればなるほど情報が希薄化され,さらには長いメールは読んでさえもらえないことも起こり得ます。
現状と課題
現状においても,例えば令和5年3月23日の国立大学法人評価委員会による第3期中期目標期間の 業務の実績に関する評価結果 (https://www.mext.go.jp/content/20230323-mxt_hojinka-000028385_07.pdf)で,京都大学は研究活動における不正行為,研究費の不適切な経理,情報セキュリティマネジメント上の課題への達成状況が不十分とされています。最近では研究費不正こそ認定されていませんが,研究活動上の不正行為 (いわゆる捏造,改ざん,盗用の論文不正。以下,論文不正とします) は令和3年度以降も複数認定されています。
論文不正防止への対応とともに教員・研究者・学生への手に届く情報提供を目指して,e-ラーニング研修受講等のもととなる京都大学研究公正推進アクションプランを毎年,改正しています。アクションプランの改正に合わせて,令和3年度には研究公正パンフレット,データ保存パンフレットをゼロベースから作成し,さらには新たに中国語版も作りました。
情報伝達においては,「いつ」「誰が」「誰に」「どのように」アクションするかを伝えることが大切です。令和5年度改正版のアクションプランでは,令和4年度改正版ではあいまいだったアクションを行う主体を明確にするため,かなりの文言が修正されています。詳しくは本学の研究公正HP https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/rule/suishinで両年度改正版を見ることが出来ますので,その比較を行っていただきたいのですが,例を挙げますと次ページのようになっています。両者を比較されるとその違いに改正の意図がご理解いただけるのではないかと思います。
アクションプランに記載されている項目によっては,文科省への実施状況(何%出来ているかを含む)の報告が求められています。アクションプラン改正の意図がきちんと伝わり,それに沿ったアクションが教育・研究現場で行われているかどうか,大丈夫でしょうか。
おわりに
研究費不正も論文不正も,日頃から真面目に教育・研究を行っている皆様にとっては,一部の不届き者のことであり,自分は関係ないと思っておられると思います。一方,万一その組織の中に疑われる者が出てくると,調査や再発防止等の様々な対応のため,関係者は教育・研究どころの騒ぎではなくなってしまいます。部局キャラバンの実施報告書のまとめには「風通しの良い組織風土の醸成が途切れないよう」との文言があります。風通しの良さこそが,研究公正のみならず,研究力の向上にも寄与すると思います。そのためには,本部はどのように情報を発信し,部局さらに専攻はどのようにそれを受け取り,構成員に向けてどう展開したらよいか,考える必要があります。
(機械理工学専攻 教授)
参照
第3期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果
(令和5年3月23日付 国立大学法人評価委員会による)
https://www.mext.go.jp/content/20230323-mxt_hojinka-000028385_07.pdf
京都大学Webサイト「公正な研究活動の推進」
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/rule/suishin
■参考 京都大学研究公正推進アクションプラン(一部抜粋)
(令和4年度改正版)
②授業中の学術マナー教育
(1)学術研究の統一的な理解と,責任感と謙虚さを伴った発表を指導する。▶各部局,各授業担当教員
(2)授業の配布資料には引用元を明示することを標準とし,各教員自らが適切な引用等の模範を示す。▶各部局,各授業担当教員
(3)レポート課題等を具体的な学術マナー教育の重要な機会ととらえ,剽窃等の不正を根絶するよう,各教員が指導する。この際,不正行為の具体例を示し,不正行為が認定された場合の処分についても教員が明示する。▶各授業担当教員,各部局,国際高等教育院
(4)学部ではレポート課題に剽窃等の不正がないか教員が確認し,大学院でも学術マナー教育を行う。▶各部局
③大学院生への論文執筆教育
(1)修士・博士論文執筆前に,必ず一度は対面で研究公正の基本についてのチュートリアルを学生に受講させ,各研究科等で受講状況を記録する。あるいは代替措置として,本学が定める大学院共通科目「研究倫理・研究公正」を受講させる。▶各研究科等,国際高等教育院
(2)剽窃検知オンラインツールの利用を促進するなど,修士・博士論文における剽窃等の不正防止の取組を推進する。▶各研究科等
(令和5年度改正版)
②学術マナー教育
(1)教員に学術マナー教育資料を配布することで,以下の点を促す。▶各学部,各研究科等,国際高等教育院
・授業の配布資料には引用元を明示することを標準とし,教員自らが適切な引用等の模範を示すこと。
・学術研究の統一的な理解と,責任感と謙虚さを伴った発表を学生に指導すること。
・レポート課題等を具体的な学術マナー教育の重要な機会ととらえ,剽窃等の不正を根絶するよう学生に指導すること。不正行為の具体例や不正行為が認定された場合の処分についても明示すること。
・レポート課題等に剽窃等の不正がないか教員が確認すること。
③大学院生への論文執筆教育
(1)修士・博士論文執筆前までに,必ず一度は対面で研究公正の基本についてのチュートリアルを教員に実施させ,研究科等で実施状況を記録し,保管する。あるいは代替措置として,本学が定める大学院共通科目「研究倫理・研究公正」を学生に受講させる。▶各研究科等,国際高等教育院
(2)大学生が著者(共著者を含む。)となる論文(修士・博士論文を含む。)や大学院生のレポート課題の指導を行う際に,教員に剽窃チェックツールの利用を促し,適切な表示による引用や研究の独自性の確認等の不正防止への取組を推進する。▶各研究科等