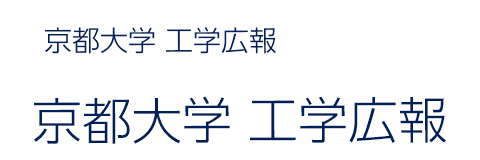光量子センシング社会実装コンソーシアムを設立!
光量子センシング社会実装コンソーシアム代表者 電子工学専攻 教授 竹内繁樹
ヨーロッパの都市に行くと,市役所や教会と隣接して大学が位置していることがよくあります。そこでは大学が,宗教,哲学から科学技術まで,都市のブレインとして,また市民の交流の場としての役割を担っていることを感じます。この度私たちは,「光量子センシング」という京都大学発祥の技術が,広く社会や学術・研究に役立てていただけることを願い,企業や研究者の交流の場として,「京都大学光量子センシング社会実装コンソーシアム (KU-PhotoniQS)」を2023年9月に設立しました。
光量子センシングとは,量子もつれ光などの「古典電磁気学では記述できない」光の状態を駆使することで,これまでの光センシングの感度限界を打破したり,まったく新しい機能を付加できる技術です。その一つが,可視域の光源と検出器のみを用いて,赤外分光を可能にする「量子赤外分光」で,分子認識可能な赤外分光装置の小型化・高感度化や時間分解計測が期待できます。文部科学省の「光・量子フラッグシッププログラム(Q-LEAP)」の支援のもと,幸い,2μm~5μmの広帯域量子FTIRの実証などに成功し,複数の企業様と現在共同研究を推進しています。
しかし,この技術を真に社会実装するには,デバイス,モジュール,システム,アプリケーションを担う様々な企業様,ならびに大学,公的研究機関の研究者により構成される「エコシステム」を構築する必要があります。そこで,オープンイノベーション(OI)機構の庄境誠様,また光量子センシング研究拠点の加賀田博司特定教授の多大なご尽力のもと,工学研究科の運営するコンソーシアムとしてKU-PhotoniQSを設立しました。

令和5年12月には,会員企業が一堂に会し「キックオフイベント」を桂ホールにて開催しました。立川康人工学研究科長のご挨拶に続いて,木村俊作OI機構副機構長および株式会社島津製作所の西本尚弘基礎基盤研究所長からの基調講演,および代表者の竹内によるセミナー講演を行いました。その後の意見交換会でも,会員企業の活発な交流が行われ,光量子センシング技術のすそ野が広がる様子が感じられました。
また,令和6年6月には,第一回年次総会を桂図書館にて開催しました。総会では,ご来賓の文部科学省の澤田和宏量子研究推進室長およびアドバイザーを代表し東京大学の荒川泰彦先生からご挨拶をいただき,続いて理化学研究所の平等拓範先生によるセミナー講演を開催しました。意見交換会では,研究員,学生によるポスター発表も実施し,産業界,大学・公研,学生まで幅広い交流を行いました。
令和6年7月時点で,会員企業は,コア会員1社,一般会員7社の合計8社にご参加頂いています。光量子センシングは,工学研究科の様々な分野で応用いただけると思われます。大学の研究者の皆様にはオブザーバー参加の制度も設けておりますので,ご興味をお持ち頂いた皆様には,ぜひコンタクトを頂けますと幸いです。最後に,設立運営に対します,成長戦略本部の鶴英明様・櫻井三夏様,桂地区事務部の皆様ならびに関係各位のご協力に感謝申し上げます。
《ホームページ》
https://www.photoniqs.oi.kyoto-u.ac.jp/