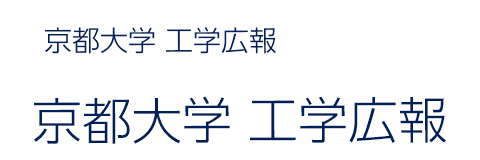変わらないために変わり続ける
工学研究科長・工学部長 立川康人

工学研究科長・工学部長を引き続き務めることになりました。微力ではありますが,工学研究科・工学部の将来に向けて全力で取り組んで参る所存です。教職員の皆様とともに工学研究科・工学部のよりよい方向を目指して進みたいと思います。ご協力を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
工学研究科・工学部が実施すべき重要事項は,歴代の研究科長が述べておられるように,工学の各分野で教育と研究を高いレベルに保ちさらに発展させてその成果を社会に還元すること,その過程を通して優秀な学生を確保し育成して社会に送り出すことにあります。人と研究成果を生み出し,それによって社会の評価を得て人と資金を引き付け,さらに新たな人と研究成果を生み出すという好循環を今後とも変わることなく機能させ,異分野に展開しながら発展していくことが我々の使命と考えます。
この2年間を振り返り,これからの1年間にどのように工学のエコシステムを発展させていくか,教職員の皆様と力を合わせて進めていきたいことを述べたいと思います。
教育改革に関連すること
着任後,工学部の新学科の設置やそれに合わせた入試の大括り化の検討を始めました。若年人口の大幅な減少を迎える今後の20年間においても社会の変化に対応しつつ高度な研究を継続して実施し,優秀な研究者・技術者を育成することが我々の使命です。そのためには,これまで以上に受験生を意識し,入学した学生の学習意欲を高いレベルに維持しながら大学院へと導く学部教育が欠かせません。工学部が扱う範囲は広く大半の高校生にとって工学部で学ぶ内容を具体的にイメージすることは容易ではありません。そこで,大括りの入試を実施して大学での学びを経て専門分野を選択するようにできないか,各学科の学科長の先生方と個別に懇談するところから開始し,学科長懇談会を定例で開催して議論を進めてきました。その過程で,入試時に学科選択する入試区分に加えて大学進学後に専門分野の選択を可能とする一括入試区分を部分的に導入して,一括入試区分では進級時に学科を選択できるような仕組みを導入することの可能性について検討を進めました。
その検討を進めていた最中に文部科学省が実施する大学・高専機能強化支援事業「高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援」への申請に取り組むことになりました。申請にあたっては関連する学科の学部生増員も検討する必要があったため,もともと議論してきた工学部の一括入試区分の検討と合わせて議論し,一括入試区分で入学した学部生が進級時に学科選択する際の配属数に柔軟性を持たせることを検討しました。最終的に一括入試区分の導入は合意には至りませんでしたが,工学部の将来を検討する会議体を設置して,工学部の初年次共通教育や入試等を含めて,工学部の将来計画を継続的に議論することとなりました。幸い,電気工学専攻・電子工学専攻の先生方のご尽力により,情報学研究科と協力して令和6年度の大学・高専機能強化支援事業に係る申請書を提出し,選定された38機関の中で京都大学のみがハイレベル枠で採択されるに至りました。
工学研究科長・工学部長になって二年目,全学的な教育改革構想の検討が教育担当理事のもとに始まり,研究科⻑部会の下に特別委員会として教育改革会議が設置され,5つのワーキンググループで議論が開始されました。ワーキンググループの検討内容を誤解なく把握して迅速に工学の意見を返すために,すべてのワーキンググループに工学執行部から委員を出すとともに各学科の学科長・コース長の先生方で構成する拡大学科長懇談会を定例で開催し,情報共有と意見交換を進めて本部に工学の要望を伝えてきました。
教育改革会議で議論されている教育改革構想は,工学のこれまでの教育内容やカリキュラムを踏まえて議論すべき点は多々ありますが,基本的な方向性は理解できるものであり,今後とも建設的に議論を進めるべきものと思います。引き続き,学部教育や学部入試については拡大学科長懇談会を通して工学部の初年次教育の在り方の基本方針を検討し,共通教育や外国語履修,要卒単位の基本的な考え方について議論を深めたいと思います。
教育カリキュラムについて,工学部初年次の情報基礎教育の共通化に進展があったことはありがたいことでした。令和7年1月実施の大学入学共通テストで「情報」が導入され,情報Iを学んだ学生が令和7年度に入学してきます。一年次の情報基礎と情報基礎演習の内容は学科ごとに違いがありますが,これを契機に初期情報教育の内容を共通化することが工学部教育制度委員会のもとに設置された工学部カリキュラム検討専門委員会(委員長:原田博司教授)で検討されました。初年次の情報基礎教育の内容を見直し,共通化して高大をシームレスに繋ぐ講義を実施することが目的です。検討結果は早速,令和7年度の講義に生かされます。工学部教育制度委員会では,特色入試についても大きな議論がなされました。令和8年度から特色入試に女性募集枠を導入します。今後,入試だけでなく,大学の支援のもとにキャンパスの環境整備も進めて参ります。
研究組織改革に関連すること
この2年間,デパートメント制に関して様々な意見交換会が開催されてきました。令和6年12月末の国際卓越研究大学申請に向けた総長メッセージで湊総長が述べられたように,学域・学系制を基本としてデパートメント制に移行し,人事と研究マネジメントを学系単位で行うことが議論されています。大講座制を実質化するとともに研究支援体制等を強化して研究者が研究に専念できる環境を確保することが研究組織改革の要点と理解しています。一方で,デパートメント制の議論とはまったく別に,工学研究科ではいくつかの専攻の大括り化を検討し,令和8年度実施に向けた準備を進めてきました。
大学・高専機能強化支援事業「高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援」による教育プログラム拡充の一環として電気工学専攻と電子工学専攻の一専攻化が検討され,化学系6専攻では従来の専攻の枠組みを大きく変える抜本的な一専攻化に向けて準備が進められています。一専攻化は,研究組織の大括り化によって従来の専攻の枠を超えた柔軟な教育研究活動を可能とし,大講座制の実質化を進める手段として有効に機能すると考えます。デパートメント制とは別の観点から専攻独自の努力によって一専攻化が進められているものですが,デパートメント制とも親和性が高く,これらの専攻が研究力をより発揮できる研究組織へと移行することが期待されます。
デパートメント制への移行を考える場合に,専攻や学系を横断する共通事項として工学研究科が実施している業務とデパートメント制での業務をどのように調整するかが重要です。デパートメント制に移行して学系の独自性をより発揮し効果を高める部分と工学研究科の共通事項として実施することによって事務効率を高められる業務とを切り分けて,デパートメント制をうまく導入する必要があります。
工学研究科には専攻を横断する研究組織があります。次世代学際院は新たな総合知の修得と実践によって次世代を担う研究者の育成を目的とする工学研究科を横断する組織です。椹木哲夫前研究科長のもとに構想が練られ,私が着任した令和5年4月1日に発足しました。横峯健彦評議員・副研究科長(原子核工学専攻教授)が初代院長を担当し,異なる専攻に所属する41名の若手研究者による活発な異分野交流が実現しています。工学研究科内の異分野交流だけでなく他部局との交流も始まりました。工学基盤教育研究センター(ERセンター)も工学研究科の共通基盤としてなくてはならない教育研究組織です。これらの共通基盤組織を工学研究科共通のコア組織としてデパートメント制のもとにうまく位置付けることが重要です。国際卓越研究大学構想を念頭に置いた魅力あるコアファシリティ構想を桂地区から提示することも重要な仕事です。コアファシリティ構想は施設整備に関するものなので,桂キャンパスの将来構想とも必然的に連動します。工学研究科の望ましい姿を桂地区事務部の事務機構を含めて描き,工程表を含めて具体的な研究組織体制を考えていくことが今年度の最重要業務となります。
工学研究科では,自由の学風のもとでこれまで誰も考えつかなかった研究が研究者それぞれの努力によって進められています。それぞれの着想を大切にして基礎研究と応用研究の両方を重視する工学研究科・工学部は,その基軸を変えることなく工学のエコシステムを機能させ発展させていく必要があります。この2年間,学内外の変化に適応するために工学研究科・工学部は自らその姿を変える努力を続けてきました。工学研究科・工学部は変わらないために変わり続けています。教職員の皆様方のご尽力に心より感謝申し上げます。
工学執行部では,この2年間,国際卓越研究大学構想の工学研究科としての提案や本部からの要請に対応するために4つの検討ワーキング(教育入試改革,研究組織改革,コアファシリティ構想,桂キャンパス構想)を設置し,執行部で分担する業務に加えて,それぞれの主査を副研究科長の先生方にお願いしました。令和7年度も基本的にこの体制を継続して諸課題に対応して参ります。引き続き,教職員の皆様の一層のご協力を賜りますよう,よろしくお願い申し上げます。
(社会基盤工学専攻 教授)
梶村正治事務部長をはじめ,桂地区(工学研究科)事務部の方々に工学研究科・工学部の運営が支えられています。令和5~6年度の執行部体制は以下のとおりでした。
〇研究科長・工学部長・教育研究評議会評議員
立川康人(社会基盤工学専攻)全般,組織改革WG主査
〇副研究科長・教育研究評議会評議員
岸田 潔(都市社会工学専攻)教育担当,教育改革WG主査(令和5年度)
蓮尾昌裕(機械理工学専攻)教育担当,教育改革WG主査(令和6年度)
横峯健彦(原子核工学専攻)研究担当,次世代学際院長,技術部長
〇副研究科長
安部武志(物質エネルギー化学専攻)国際担当,工学基盤教育研究センター長,コアファシリティ構想WG主査
小椋大輔(建築学専攻)評価・財務・施設・男女共同参画担当,桂キャンパス構想WG主査
川上養一(電子工学専攻)研究倫理・研究公正・図書・広報・情報担当
高橋良和(社会基盤工学専攻)学生担当
〇桂地区事務部
事務部長 梶村正治
総務課長 大野広道
管理課長 馬場 勉(令和5年度),松井芳樹(令和6年度)
経理課長 道上吾朗
教務課長 廣瀬泰子
学術協力課長 南口敬司(令和5年度),中川憲一(令和6年度)