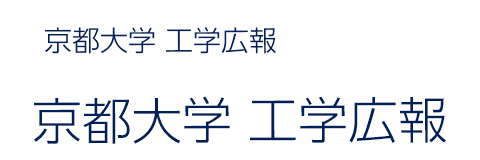桂キャンパスに女子中高生とその保護者が250人! ―第19回「女子中高生のための関西科学塾」の実施―
関西科学塾実行委員長 電気電子工学科 准教授 掛谷一弘
「女子中高生のための関西科学塾」は関西地区5国公立大学(大阪大学,大阪公立大学,神戸大学,奈良女子大学,京都大学)の理工系学部の教員を中心に2006年から実施されている,女子中高生の進路選択を支援する事業です。現在の実施体制は,上記参加大学が1年ずつ輪番で幹事校を務め,AからFの6日程を実施しています。A日程,F日程は幹事校でのイベント実施,C,D日程はほかの会員校でのイベント実施,B,E日程は協賛企業訪問などの大学外でのイベントを実施しています。運営資金は一般社団法人関西科学塾コンソーシアムが協賛企業から集めた資金を幹事校に寄付するほか,実施大学での男女共同参画関連事業からの金銭的な支援を受けています。これらは実施大学での実行委員の判断で進められており,年に3度の関西科学塾実行委員会で大学間の意思疎通が図られています。
京都大学ではこれまでに何度か幹事校を実施してきましたが,いずれも理学部が担当しており,今年度初めて工学部が実施担当部局になりました。まず,2024年3月に工学部各学科から実施委員を出していただき,役割分担を行いました。以前より関西科学塾に講座を提供している平山朋子教授(物理工学科)と小職に加え,寺村謙太郎教授(理工化学科)でA日程の企画運営を行い,上原恵理香講師(情報学科)と神谷奈々助教(地球工学科)にF日程の実験講座を新たにご担当いただくという前提で進めることにしました。
A日程では,桂キャンパスになるべく多くの女子中高生とその関係者に来てもらおうと,魅力的なプログラムを作成することに腐心しました。まず,講演会会場を船井哲良記念講堂に設定し,学会や学内関係者を通じて講演者を募り,企業技術者,本学助教,企業技術者かつ社会人博士課程,本学卒業生かつ国研幹部研究者という,所属・分野・年齢層の多様な方に講演をお願いしました。講演後には,会場の女子中高生からも数多くの質問が出ました。

講演会に引き続き,女子中高生は大学生・大学院生,教員との交流会に移りました。交流会会場の桂図書館リサーチコモンズでは,京都市街地を一望できる部屋で参加者と学生・教員で各々10名程度の18のグループが,大学進学などについてグループトークを行いました。並行して船井講堂では同伴の保護者からの質問に,上記工学部教員3名に立川学部長と廣瀬教務課長を加えた本学教職員,他大学からの関西科学塾実行委員が回答する懇談会が実施されました。懇談会では,中高一貫校での学修意欲の向上へのヒントといった一般的な質問から,各教員所属大学または部局において企業就職に関する教育が現在どのように行われているのか,などといった具体的な問いまでがあり,工学部をはじめとする理系学部進学に関して保護者の興味も高まっているという印象を受けました。終了後の参加者アンケートからは,工学部卒業後の職業人としてのイメージが,医学部や薬学部に比べて薄かったのが講演や交流会への参加によって明確に持てるようになった,という意見があり,工学部での教育や高大連携の在り方について多くの示唆を得たと思っています。
本稿が出版される直前の3月22,23日には吉田キャンパスでF日程の実施を予定しております。ここでは,工学部の教員だけでなく,理学,農学,総人などの多くの先生方にもご協力をいただき,中高生向けの実験講座と発表会を行う予定です。これについては別の機会に紹介したいと思います。
私が関西科学塾の活動にかかわっているのは,2022年度からですが,それによってはじめてわかったことをここに挙げたいと思います。まず,進路選択の意識づけは中学生時代の経験が一番重要であるということ。その時期に自分が将来活躍できそうな分野をイメージできることが必要だと思います。並行して,その意思を否定するような無意識のバイアスが取り去られれば,自由な意思選択ができるのではないかと思います。
また,本事業に関連して,マスメディア露出を,KBSラジオ,NHKラジオ,京都新聞,朝日新聞で行いました。A日程講演者である秋山みどり助教(理工化学科)には先頭になってこの労を取っていただきました。最後になりましたが,F日程を含めた本年度の事業実施にご尽力いただきました工学部はじめ学内各部局の教員各位,工学部教務課各位に厚く御礼を申し上げます。