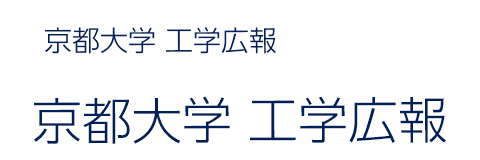「京都大学 次世代研究者産学連携ネットワークイベント:BX桂」開催報告 ―テクノサイエンスヒル桂構想に関わる取組み(令和6年度の活動成果)―
京都大学桂キャンパスでは,イノベーション創出基盤の創成や産学連携ネットワーク構築の基盤となる“テクノサイエンスヒル桂構想の実現”を目指し,工学研究科を中心に桂図書館1),総合研究推進本部が連携し,研究者の研究シーズを可視化・発信するための各種取組み2)~6)を展開しています。
上記取組み推進の一環として,これまでに大学・企業における理工系女性研究者の産学連携ネットワークイベント:「桂ジェネ4)」「Meジェネ6)」の他,企業・大学若手研究者による産学連携ネットワークイベント:「Fostering桂」「Transform桂」を開催してきましたが,今回,令和6年度最初のイベントとし,バイオ技術を活用した社会変革技術(BX:バイオトランスフォーメーション)をテーマとする次世代研究者産学連携ネットワークイベント「BX桂」を企画・開催しました。本イベントでは,レッドバイオ(医療・健康),ホワイトバイオ(バイオものづくり),グリーンバイオ(農林水産業等)の分野でBXに関わる企業,京都大学の次世代研究者を招き,研究発表,オープンディスカッション,展示を行いました。BXをテーマとした相互議論の場を提供することで,産学の協働や次世代人材育成への貢献を図ることを趣旨としたイベントで,産業界・学術界等からオンラインを含め,141名の参加がありました。


(画像1)イベントチラシ
研究発表(画像2)では,京都大学,ベンチャー企業の方から4名の方にご登壇頂き,レッドバイオの分野では工学研究科 窪田講師から「細胞から着想を得た超分子ヒドロゲル材料の構造と機能」と題し,多成分系超分子ヒドロゲルのネットワーク構造制御や薬物徐放機能について,(株)サイフューズ 秋枝氏からは「産学官で創出する新しい社会~バイオ3Dプリンタを用いた再生医療~」と題し,世界初の技術による細胞のみで作製した組織・臓器等製品の先端医療分野への事業展開について発表いただきました。ホワイトバイオ・レッドバイオに関連する分野では,農学研究科 宋和助教より「酸化還元酵素と電気を融合したバイオミメティックス」と題し,バイオセンサーやCO2バイオ資源化に関する研究を,グリーンバイオの分野では(株)プランテックス 山田氏から「都市型植物生産産業の創出への挑戦」と題し,高度なモノづくり技術による持続可能社会の実現を目指した植物工場の最先端事情について紹介頂きました。会場やオンラインから技術的な内容の他,事業展開等について多くの質問があり,発表への関心の高さがうかがえました。

研究発表の後のオープンディスカッションでは,それぞれの発表内容を更に深くお聞きするとともに,研究開発のきっかけや,今年閣議決定された「バイオエコノミー戦略」に触れ,BXを進めるうえで重要な人材育成や投資を加速するためのポイント,イノベーションに繋がる技術等について更にお話しをうかがいました。人材育成に関しては,“最先端技術を支える倫理観”,“一つの分野に縛られないマルチタレント”がキーワードとして挙がり,イノベーションに繋がる技術については各々の分野での連携について話が展開されました。オンラインからの質問も受けながら,終始和やかな雰囲気のもと,活発な意見交換となりました。オープンディスカッション後の展示では,各ブースともイベント参加者と登壇者の交流で大変賑わい,イベントは成功裏に終了しました(画像3)。
これら一連のイベントは,その時々の政策や技術動向を踏まえたテーマを設定し,そのテーマに関する相互議論の場を提供することで,産学の協働や次世代人材育成への貢献を図ることを趣旨としています。今後もこのようなイベントの企画・開催を通じて,イノベーション創出基盤の創成や産学連携ネットワークの構築を推進していきます。