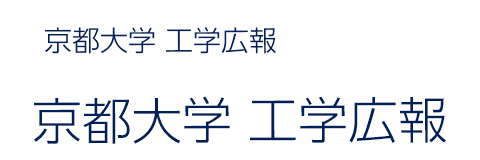工学におけるフロリダ大学との国際交流事業
附属工学基盤教育研究センター(以下,ERセンター)の重要なミッションである国際化推進の一環として,学生交流協定が締結されているフロリダ大学(以下,UF)の教員と多くのUF学生を受け入れています。UF学生に京都大学,京都,そして日本について幅広く学んでもらう機会を提供すると共に,本学学生には多文化共生の精神と国際感覚の涵養を促すために,講義や文化イベントを通じて交流を進めてきました。本稿では,2024年度のUF交流事業について紹介します。
本題の前に,これまでの経緯を簡単に紹介します。2021年に”Cross-Cultural Engineering Seminar Series”と称する全6回のオンラインセミナーを10,11月にUFと本学で共同実施し,コロナ禍で色々と制限が多い中でもSTEM分野における交流を深めました。2022年には学部4回生から修士1回生相当の学生14名を短期交流学生として6,7月に桂キャンパスに受け入れました。2023年は教員と32名の学生が同時期に2ヶ月ほど京都に滞在していたのですが,手続き上のことから本学との交流は6月29日の1日だけとなりました。
2024年は6月3日から7月30日まで,UFの教員1名,TA2名,学生49名を桂キャンパスに受け入れ,滞在期間中は月曜から木曜まで,朝から午後1時頃まで桂ホールを拠点にしていました。学生たちには短期交流学生の身分を付与し,桂図書館など京都大学の施設を利用して貰いました。受け入れに際して,教員間ではUFのJeremiah Blanchard准教授,ERセンターの私とコウハクル講師の三者で密に打合せを行い,滞在中に実施する事業や各種イベントの企画を進めてきました。単発や継続的なものを含めて主に以下のような取り組みを実施しました。
1.滞在期間中 UFの教員とTAによる3科目の講義を実施(UF主催)
2.滞在期間中 工学研究科共通型授業科目『実践的科学英語演習Ⅰ』へのUF学生参画と共同プロジェクトの実施(ERセンター主催)
3.滞在期間中毎週月曜日 ランチネットワーキング(ERセンター主催)
4.6月14日,7月19日 書道・茶道教室(UF主催)
5.6月27日 日本文化フェスティバル(ERセンター,UF共催)
6.7月25日 2.の講義における成果発表会(ERセンター,UF共催)
1.については,“Cross Cultural Engineering”,“Performant Programming”,“3D Engine in Practice”のUFの3講義を桂ホールで実施し,事前登録制としつつも本学学生は誰でも参加できるようにしていました。告知期間は当初設定より延長したのですが申し込みが少なく,最大で12名の登録に留まり,登録者は大半が留学生でした。3.ランチネットワーキングは本学留学生同士の交流を促進するために実施していたものを,UF学生にも拡大したものです。平均して本学学生は20名程度(日本人比率は半分くらい)参加し,同年代同士ということもあり話が弾んでいました。4.,5.は単発の文化交流イベントです。UF主催の4.茶道教室では京都在住の米国人の茶道師範に教授して貰ったことで,UF学生にはとても分かりやすく,日本人の私にとっても学びが多いイベントでした。5.日本文化フェスティバルでは和太鼓,雅楽,浴衣着付け,和ろうそく,書道,折り紙といった日本文化を感じて貰えるイベントを多数実施し,本学学生にも多く参加して貰えました。和太鼓は昼休みに事務管理棟前にて実施したため,ご覧になった方もいたのではないでしょうか。2.,6.では『実践的科学英語演習Ⅰ』でテーマにしていた災害予防についての英語での学習成果をプログラミングとアートに長けたUF学生のプロジェクトに反映させるという新しい試みを実施しました。両者のコラボレーションは大変うまくいき,その中の1グループは2024年12月の米国Serious Games Showcase & Challenge (SGS&C)という教育・訓練用ゲームの大会において学生部門第一位に輝きました。受賞グループ紹介ページでは,本作品は京大との共同作業で生まれたものと書かれており,当該グループに関わっていた2名の本学学生の名前も記載されています。UFと交流を進めてきたことが一つの成果に結び付いたことを嬉しく思います。最後になりましたが,受け入れに際して教務課を中心とした桂地区事務部の多大なご支援があったことに感謝申し上げます。
本年度実施したことによる課題としては,本学の日本人学生の参画がかなり少なかったことが挙げられます。日本人学生には英語で話すことを恐れず,積極的に交流に参加してくれることを期待します。2025年度は,UFの学部生は吉田,大学院生は桂に受け入れる形で進めるべく国際高等教育院と打合せを行っております。
本事業へのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。