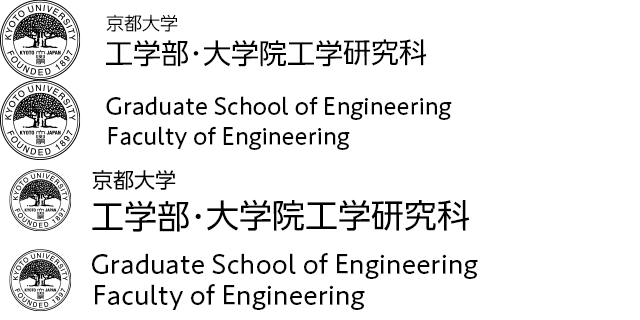第一原理計算を基に理想的な光触媒-助触媒界面を設計 ―酸ハロゲン化物光触媒の酸素生成効率を劇的に向上―
物質エネルギー化学専攻の鈴木 肇 助教(青藍プログラム)、南本 健吾 修士課程学生(当時)、阿部 竜 教授らの研究グループは、岡山大学 山方 啓 教授、KEK 物質構造科学研究所 野澤 俊介 准教授と共同で、第一原理計算を基に理想的な光触媒-助触媒界面を設計することで、酸ハロゲン化物光触媒の酸素生成効率を大幅に向上させることに成功しました。
半導体光触媒を用いた水分解は、太陽光を活用したクリーンな水素製造法として注目されており、その高効率化に向けた多様なアプローチが検討されています。なかでも、表面反応を担う助触媒(金属種微粒子)の設計は極めて重要ですが、光触媒-助触媒界面の構造や機能の理解は不十分であり、従来は経験に基づいた試行錯誤による最適化が主流でした。本研究では、層状構造を有する酸ハロゲン化物をモデル光触媒とし、第一原理計算から予想された電荷分離状態に基づいて、正孔の集積しやすい層を選択的に露出させ、そこに高活性な助触媒(酸化イリジウム)を担持する界面設計を行いました。その結果、正孔の移動が促進され、未処理試料に比べて酸素生成速度が飛躍的に向上し、可視光照射下で16%という高い反応量子収率を達成しました。
本研究で得られた知見は、酸ハロゲン化物に限らず、広範な光触媒における界面構造の合理設計の可能性を示すものであり、今後の人工光合成技術や太陽光水素製造の高効率化に大きな貢献が期待されます。
本研究成果は、2025年6月19日に、国際学術誌「Journal of the American Chemical Society」にオンライン掲載されました。
研究詳細
第一原理計算を基に理想的な光触媒-助触媒界面を設計 ―酸ハロゲン化物光触媒の酸素生成効率を劇的に向上―
研究者情報
- 鈴木 肇 京都大学教育研究活動データベース
- 阿部 竜 京都大学教育研究活動データベース
書誌情報
| タイトル |
Interface Engineering between Photocatalyst and Cocatalyst: A Strategy for Enhancing Interfacial Charge Transfer and Water Oxidation of Layered Oxyhalides (光触媒-助触媒間の界面エンジニアリング:層状酸ハロゲン化物光触媒の界面電荷移動・酸素生成能の向上) |
|---|---|
| 著者 |
Hajime Suzuki, Kengo Minamimoto, Yusuke Ishii, Osamu Tomita, Akinobu Nakada, Shunsuke Nozawa, Akira Yamakata, Ryu Abe |
| 掲載誌 |
Journal of the American Chemical Society |
| DOI | 10.1021/jacs.5c05452 |
| KURENAI | ー |