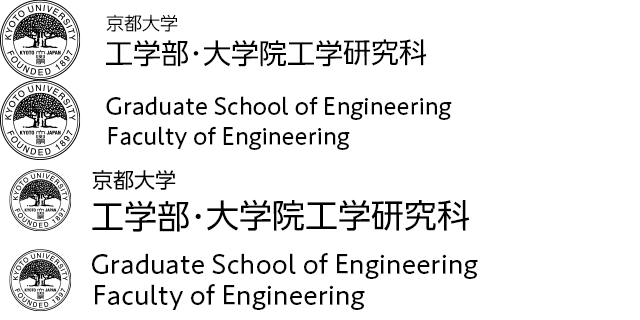放射線による発がんリスクの“出発点”に迫る!―DNA周囲の水の分解が生命の遺伝情報を狂わせる―
【発表のポイント】
- 低線量域の放射線による発がんリスクは、仮定を用いたモデルで推定されています。モデルには発がんを引き起こす線量にしきい値が有るものと無いものがあり、どちらのモデルが正しいか長年解明が望まれています。
- 本研究では、発がんの出発点であるDNA損傷とDNA周辺の水分子と放射線の関係に注目し、シミュレーションによりDNA損傷のメカニズムを解析しました。
- 計算の結果、放射線で分解された水分子から発生した電子やOHラジカルが同時にDNAと反応することで、DNAを複雑に損傷し得ることを明らかにしました。この結果は、発がんリスクにしきい値が無いモデルを支持しています(図1(d))。
- 本研究によるDNA損傷のメカニズム解明は、放射線防護の基礎概念になることが期待できます。
【概要】
本研究では、DNA周囲の水分子の放射線分解生成物が生命の遺伝情報を狂わせる可能性を示しました。この結果は、放射線被ばくによる発がんの出発点に新たな基礎概念を与える研究成果です。
放射線による発がんリスクは、低線量域では疫学データが少ないため、モデルに基づいて推定します。モデルの中には、低線量でも発がんリスクがあると考える“しきい値が無いモデル”(図1(d);黒破線)や、その逆の“しきい値が有るモデル”(図1(d);緑破線)が存在します。現在では、どんなに低線量でも発がんリスクが存在すると見なす“しきい値が無いモデル”を採用し、安全性に余裕を持った放射線管理が行われています。放射線による発がんリスクを理解・評価するには様々な過程の科学的知見の蓄積が必要ですが、発がんの出発点であるDNA損傷の実験的検出は未だ非常に困難です。
本研究では、計算機シミュレーションを利用して、複雑なDNA損傷の形成メカニズムの解明を目指しました。DNA損傷は放射線との直接・間接作用により形成されますが、ここでは主要因である間接作用に注目しました(図1)。このとき水分子の放射線分解で生成されるOHラジカルや水和電子(e−aq)はDNAと反応し、DNA鎖の切断や塩基の損傷などを引き起こす特徴があります。そこで、水分子の分解生成物のランダムな運動を模擬し、DNAと反応してDNAの損傷が発生する確率を計算しました。
その結果、DNA近傍の水分子が分解された場合、修復可能な孤立損傷に比べ約50分の1の確率で鎖切断と塩基損傷が密に生じた複雑なDNA損傷(クラスター損傷)が形成されることを解明しました。このような複雑な損傷が形成されると、DNA修復酵素による損傷の修復が困難になり、細胞の染色体異常が誘発され、最終的に発がんに繋がる可能性が生じます。本研究成果は、発がんリスクの“しきい値が無いモデル”を支持する結果となりました。この知見は今後、放射線防護の新たな基礎概念になることが期待できます。また本研究では、DNA損傷の観点から低線量被ばくの理解を深めました。今後は、放射線治療で重要となる高線量放射線場におけるDNA損傷の収量評価等にも展開する予定です。
本研究は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(理事長 小口正範)原子力基礎工学研究センターの甲斐健師研究主幹ら、茨城大学(学長 太田寛行)大学院理工学研究科 量子線科学専攻の横谷明徳教授並びに伊東祐真氏、北海道大学(総長 寳金清博)大学院保健科学研究院の松谷悠佑講師及び京都大学(総長 湊長博)大学院工学研究科 附属量子理工学教育研究センターの土田秀次准教授との共同研究によるものです。
本研究成果は、2025年3月6日(ロンドン時間10:00)にNature Portfolioの『Communications Chemistry』に掲載されました。
研究詳細
放射線による発がんリスクの“出発点”に迫る!―DNA周囲の水の分解が生命の遺伝情報を狂わせる―
研究者情報
- 土田 秀次 京都大学教育研究活動データベース
書誌情報
| タイトル |
Multiple DNA damages induced by water radiolysis demonstrated using a dynamic Monte Carlo code |
|---|---|
| 著者 |
Takeshi Kai, Tomohiro Toigawa, Yusuke Matsuya, Yuho Hirata, Hidetsugu Tsuchida, Yuma Ito, Akinari Yokoya |
| 掲載誌 |
Communications Chemistry (Nature Portfolio) |
| DOI | ー |
| KURENAI | ー |