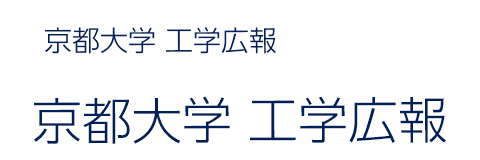工学ウェブサイトの運用に携わって
技術専門職員 奥中敬浩

私は1999年4月に京都大学工学部情報学科に入学し,情報学研究科数理工学専攻の修士課程を修了後,2005年4月に工学研究科附属情報センターに採用されました。伊賀の片田舎から京都にきて以来,京都大学には25年間お世話になっています。私の所属する情報センターは,工学研究科の情報基盤の運営を行う組織として設立されたセンターで,工学全体に向けたサービスを提供しています。採用された当時は設立後間もない頃で,新しいサービスを模索することも多くありました。そんな中,学生時代にウェブサイトを作った経験があったこともあってか,ウェブ関連の業務を担当するようになっていきました。工学ウェブサイトは1996年には既に存在したようです。当時高校生だった私は,工学ウェブサイトを大学選びの参考に...してはいません。まだそのような時代ではありませんでした。
現在の工学ウェブサイトは,部局としてのサイトをはじめ,学科・コース・専攻等のサイト(約50サイト)を統一的な見た目や枠組みで運用しています。これは,2008年4月にコンテンツの充実を目的として,広報委員会を中心に行われたウェブサイト刷新が始まりです。情報センターとしては,ウェブサーバ集約による効率化,コンテンツマネジメントシステム導入による編集環境の整備といった技術的な面から協力し,広報担当の方がコンテンツに集中できる環境を整えました。当時はスマートフォンもまだ普及していなかった時代で,学内でも先進的な取り組みでした。それ以降,物理的なサーバ運用や,システム構築,ウェブデザイン制作,追加機能の開発,利用者サポートなどを情報センターの内製で行っています。
ウェブサイトは構築して終わりではなく,その後の運用も重要です。この16年間,求められるコンテンツは変化し,技術面でもモバイルでの閲覧が主流になるなど大きく変わってきました。課題があれば広報担当の方と一緒により良い形を考え,大小の改修を繰り返して現在に至ります。しかし大学のウェブサイトの目的は何かを考えると,ECサイトの商品販売のように単純なものではなく,難しいなという思いは今でも変わっていません。
最後に,ウェブサイトを運用する中で,グリコや牛乳石鹸のデザインを考案された奥村昭夫先生にご意見を伺う機会がありました。その時お聞きした言葉がとても印象に残っています。
「デザインとはデザインしないこと」
デザインは凝ったイラストや飾りつけをすれば良いのではなく,目的達成のために本当に必要なところにデザインを施し,必要のないところにはデザインしないことも大事,という意味です。ウェブに限らず何かを作る際は,私の中で指針になっています。
(附属情報センター)