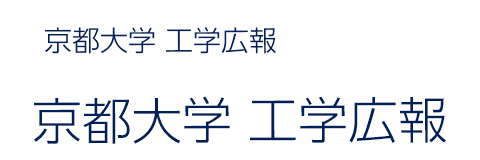持続可能な建築を目指して
助教 山田諒

私は2019年に京都大学工学部建築学科を卒業し,2021年に同大学大学院建築学専攻で修士(工学)を取得,2024年に博士(工学)を取得しました。ありがたいことに,学位取得に至るまでの6年間お世話になった西山・谷研究室で引き続き研究を継続する機会をいただき,2024年4月より京都大学大学院工学研究科の助教に着任しました。
現在,私は主に鉄筋コンクリート構造およびプレストレストコンクリート構造に関する研究を行っています。これらの構造形式によって設計された建物の地震時の損傷の進展や,柱や梁などの部材の強度を載荷実験や数値解析を通じて検証しています。載荷実験では,実際の部材を模擬した試験体を作製し,油圧ジャッキ等で加力を行い,破壊に至るまでの過程を計測・観察し,そのメカニズムを解明します。また,数値解析ではこれらの実験結果を再現することで妥当性を確保し,様々な状況をシミュレーションして建物や部材の理解を深めます。以上の検討結果に基づき,地震等の災害時の被害を未然に防ぐための設計法を検討しています。これらの研究成果は,最終的に日本国内の設計法に反映され,より強靭な国土基盤の構築に寄与します。
以上の従来の研究に加え,最近は新たな試みとしてアンボンドプレキャストプレストレストコンクリート(以下,アンボンドPCaPC)構造の普及および詳細な計測に基づく損傷評価の2点に重点を置いて研究を進めています。前者の研究は,部材品質の向上,工期の短縮等の利点を持つプレキャスト(PCa)工法と,コンクリートのひび割れ抑制や原点指向性等の利点を持つプレストレストコンクリート(PC)構造を組み合わせたPCaPC構造において,PC鋼棒をアンボンド化したアンボンドPCaPC構造に関するものです。この構造は建物供用終了後の部材の解体や再利用が可能で,持続可能な開発に貢献します。後者の研究は光ファイバセンサやモーションキャプチャ,画像計測等の新たな計測手法を駆使し,コンクリートに生じるひび割れや内部の鉄筋のひずみ等を連続的かつ詳細に計測します。これにより,ひび割れ等の発生箇所の特定が難しい鉄筋コンクリート構造やPC構造において,災害後の建物の残存性能をより正確に評価し,迅速な復旧を可能にします。
いずれの研究も,日本という地震大国において,持続可能な開発目標に沿った建築物の建設を目指しています。近年,2011年東北地方太平洋沖地震,2016年熊本地震,2024年能登半島地震など,大地震による被害が絶えません。これらの被害を少しでも減らすことを目標に,日々研究を行っています。最後になりますが,少しでも多くの人にこの分野に興味を持っていただけるよう,日々研究に邁進してまいりますので,今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
(建築学専攻)