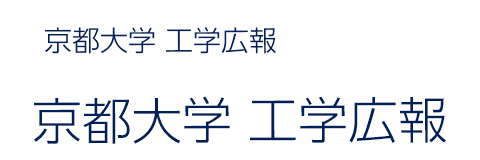鋼構造の巨人の背中を追いかけて
名誉教授 杉浦邦征

1988年11月16日付けで京都大学工学部土木工学科構造力学講座助手として着任して以来,京都大学において,36年4カ月と15日の月日を過ごしました。その間,工学研究科においては,土木工学専攻(構造力学講座),土木システム工学専攻・都市環境工学専攻(複合構造デザイン講座),社会基盤工学専攻(構造工学講座構造力学分野),都市社会工学専攻(構造物マネジメント工学講座)と所属を変えて,また,学際的組織でもある地球環境学堂(環境基盤エンジニアリング論分野)にも関わり,研究・教育を行ってきました。京都大学の皆様には,大変お世話になりました。この場を借りて深くお礼申し上げます。
さて,私は,1982年3月に名古屋大学工学部土木工学科を卒業,1982年4月より同大学工学研究科博士前期課程・博士後期課程(土木工学専攻)で学び,博士1回生の夏に米国New York州立大学Buffalo校(SUNYAB)に留学しました。修士1回生夏季休暇時に,Golden Gate橋を見たさに,鋼構造を学ぶ同級生3名で,関西の私立大学が企画したホームステイプログラムに参加し,米国California州San Francisco市から車で東に約40分程に位置するWalnut Creek市で,Dunlap家の皆さん(ご夫婦と息子,娘と犬1匹)と過ごした約1カ月間が初海外でした。ご主人は,システムエンジニアで,United AirlinesからBank of Americaに転職されたタイミングでしたが,ボーイング747の整備工場の見学,航空機コクピットへの立入などを経験しました。また,奥さんは,Community Collegeの教授で,専門はHumanityでしたが,講義などを聴講させてもらいました。UCBerkeley視察,SFGiants観戦も含めて自由な社会に触れたこの経験が留学を目指す原点であったかと思います。ホームステイ後,Los Angelesに移動し,海水浴・Universal Studios Hollywood・Disneyland Parkで楽しみすぎたのか,帰国してからも魂の抜けた状態が続いたと記憶しています。私は,京都大学工学部土木工学科橋梁工学研究室出身の福本唀士教授が担任する土木工学科第一講座において,卒業研究・修士研究に取り組んでいましたが,福本先生がFulbright Fellow Programで,第二次大戦後の鋼構造研究の拠点であった米国Lehigh大学に留学され,Ph.D.の学位を取得後に,名古屋大学に着任された関係で,世界の多くの鋼構造分野の先生方と親交があり,例えば,杉浦が在籍時でも,ベルリン工科大学・Lindner教授,シドニー大学・Trahair教授,Nottingham大学・Nethercot教授などを名古屋大学に招致されていました。世界で鋼構造(耐荷力)分野をリードする研究者と触れ合う機会が多くあったのも結果として留学の道に歩みだした一因と思います。
SUNYABは,QS世界大学ランキングでは,100番以内にも入らず,米国の著名な公立・私立大学とは比べられませんが,UB School of Engineering and Applied SciencesのDeanでありSupervisorであったG.C.Lee教授(耐荷力)から,教育費(授業料・生活費)に対して受けられる教育レベルでは米国トップクラスであるとお聞きしました。総合力としては見劣りしますが,特定の専門分野では,優れた研究教育で実績がある教授陣がいるといった状況と理解しています。科目履修では,講義内容に評判が高い他専攻の力学関連科目(非弾性応力解析,熱応力,複合材料など)を積極的に受けに行きました。SUNYABへの留学の誘い水は,Lehigh大学で福本先生のクラスメイトであったLee先生がトヨタ工場の視察で福本先生を訪問された折りに,SUNYABの新しい取り組みに際して日本からの留学生を受け入れる用意があると申し出られたためとお聞きしてます。なるほど,SUNYABの学長として大学の成長戦略のため,新キャンパス建設を実現させた同じLehigh大学出身のR.L.Ketter教授(鋼構造)の取組もあり,地震工学分野で実績のある大学と競い合うために,新キャンパスでは高性能な振動台,複合載荷試験機などの先端設備を導入し,構造実験棟を一新する状況下であったかと思います。結果として,最初の国立地震工学研究センターの誘致に成功され,多くの新スタッフが採用され,各国から多くの研究者が共同研究のためにSUNYABを訪れました。私の取り組んだ研究も地震時応答を想定した鋼の繰り返し非弾性構成則と低サイクル疲労破壊に関するものでした。Lee先生の下では,振動台制御のための構造システム同定法,水と構造体(ダム)との連成振動解析,組合せ荷重下での塑性ヒンジ挙動,寒冷地での構造物挙動などが進められており,変わり種では,肺の有限要素解析をしていた学生もいました。
実験室,計算機センターと図書館を主活動場として,4年の歳月をかけて,何とかPh.D.の学位を取得し,ポスドクで短期間,研究員としてつなぎ,ご縁あって,渡邊英一教授が担任する京都大学構造力学研究室に着任するため帰国しました。1961年に設置された名古屋大学工学部土木工学科の組織運営にご尽力され,私も構造力学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)を学んだ『成岡昌夫教授』が,名古屋大学への配置換え前に担任していた講座で,教育・研究に携わることとなりました。高齢にもかかわらず成岡先生は,吉田キャンパスの土木工学科図書室まで文献調査に頻繁にお越しになられ,休憩時に私の居室にて,雑談しながら一緒にお茶を頂いたことを懐かしく思います。その当時,本四架橋および阪高湾岸線の建設がピークで,日本における鋼構造(橋梁工学)の研究重心は関西にありました。恩師の福本先生は,私が留学中に名古屋大学から大阪大学に移られており,京都大学では,山田善一教授(耐震工学)・白石成人教授(構造信頼性)・渡邊英一教授(耐荷力)・松本勝教授(風工学),大阪市立大学の中井博教授と北田敏行教授(橋梁工学,耐荷力),大阪大学の西村宣男教授(構造解析学)と松井繁之教授(複合構造)と川谷充郎教授(構造動力学),関西大学の三上市蔵教授(桁耐荷力),大阪工業大学の栗田章光教授(複合構造),立命館大学の小林紘士教授(風工学),近畿大学の谷平勉教授(接合工学)らが挙げられるように,鋼構造分野の先端研究を競い合い,一方で,毎年秋に開催される関西鋼構造野球大会(現在は,ソフトボール大会に変更)では,研究者・学生間交流を積極的に行っていた環境がありました。また,コンクリート構造で著名なF. Leonhardt先生から,『良い設計は競争の賜物です』とお聞きし,90歳のご年齢でも設計業務を行う姿勢に感銘を受けました。こうした教授の方々の背中を追って,将来の自分がどこまで到達できるか不安な一面もありました。
京都大学における最初の大きな節目は,JICA(国際協力機構)が立ち上げたジョモケニヤッタ農工大学プロジェクト(約20年間の実績がある)において,1994年から土木工学科・構造工学分野の指導に関わり,それ以降,2000年にプロジェクトが終了するまで毎年1~2か月現地にて,教員・学生への研究指導を30歳台で経験したことです。同世代の地盤工学分野の木村亮教授に加えて,プロジェクトに関わるJICA長期・短期専門家との交流は新鮮なもので,慌ただしい日本国内での活動をしばらく忘れ,アフリカ時間でゆったりとした毎日を送ることで,『命の洗濯』と言っていたことが懐かしく思い出されます。自身の留学時は,研究に必要な時にのみ英語を用いましたが,講義・研究指導を英語で行えたことは,その後の教育・研究活動,多様な交流の展開へと役立てることができました。最初の渡ケニア時にご挨拶に伺った中川博次教授(当時は工学部長で,プロジェクト国内委員会委員長)からの『優れた研究成果を積み上げるだけでなく,このような国際的な活動も京都大学教員として評価される時代が来る』との,御言葉は心に留めております。
渡邊先生の指導の下,京大を訪問された上海交通大学・沈為平教授,トレント大学・Zandonini教授,ピッツバーグ大学・Bjorhovde教授をはじめとする外国人来学者とも交流できましたし,次の世代を担う大学での教育研究者の育成に意義を感じた訳ですが,私の30~40歳台頃の研究で苦楽を共にした,約10年下の世代では,6名の大学教員が国内で大いに活躍されています。しかし,40歳半ばを迎え,2006年10月に構造力学研究室を担任する機会が与えられて以降,自身の責任で,研究遂行および次世代を育てる難しさを痛感しました。50歳を過ぎ,教授としての学内用務で学生と向き合える時間が減り,直接研究を手掛ける機会が減り,隅々まで指導も行き届かず,悩んだ末に,技術士の資格を取得したことを受けて,恩師の福本先生宅に押し掛け,大学を辞職して,実践的な活動を目指すことを検討中と申し上げたところ,雑談は長時間となり夕食時まで及び,結果として『後進を育てることに専念しましょう!』と促された感で帰宅した覚えがあり,目標設定の転機となりました。関東の某大学の長老教授から『あなたには京大教授は務まらない』とも言われましたが,同世代の方々ならびに研究室OBの後進とともに歩みながら,一方で,研究室内での准教授・助教の先生方との協働もうまく回り始め,外国人留学生の博士学生のみでなく,日本人の博士学生も多く支援することとなりました。将来を支える日本人5名が准教授・助教として活躍しております。留学生も学位取得後に母国に帰り,5名が大学で教育研究に従事しております。
これまで指導した外国人留学生の帰国後の活動を支援するため,ケニア,モザンビーク,ミヤンマーなど途上国での現地研究にも取り組んできました。2020年から数年の間,新型コロナ禍で制約がありましたが,一昨年頃から,国際会議への参加など海外での研究活動が以前のような状況に戻りつつあります。若手の育成も視野に,これまでに訪れた経験の無い国・都市へも伺い,国際的な研究者間交流の一層の進展に向けて再スタートした時に定年退職を迎えましたが,欧米諸国の研究テーマのダイナミズムと戦略的集中を感じるとともに,途上国の研究者などの精力的な取り組みを目のあたりにし,本学の若手研究者の世界における活躍に期待したいと願います。
(都市社会工学専攻 2025年3月退職)