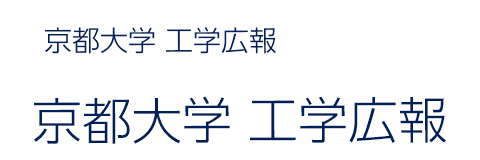学生との対話:「質問と回答による対話」その後
名誉教授 西山峰広

“Shift response”と“Support response”という言葉を聞いたことがあるでしょうか?話し手が言ったことに対して,それを“shift”する,つまり,聞き手が自分の話題に引き寄せようとする応答と,"support”してさらに話を引き出すような応答をすることをいいます。例えば,「昨夜,子どもが熱を出して病院に連れて行ったんです。」という話し手に対して,「うちの子も1週間前に熱を出して大変でした。」という“shift”する応答と,「大変だったでしょう。お子さんはその後どんな様子ですか?」と,“support”する応答だと言えば,わかっていただけると思います。“support response"すると話し手が話しやすくなり,どんどん聞き手に情報を伝えます。もちろん聞き手から少しは周辺情報を提供し話し手が話しやすくする必要はあります。
「質問力」あるいは「聞く力」という言葉が使われることがあります。“support response”できる人は聞き上手で話し手から多くの情報を得ることができます。私は自分から話すよりも聞く方を好みますが,“shift response”ばかりの相手には話す気が失せてしまいます。
2019年10月の工学広報に「質問と回答による対話」と題した拙文が掲載されました。講義後に提出させる質問票に対してすべての質問に回答し,1週間後の次の講義において一覧を配布します。これを十数年続けてきました。講義での説明に対して“support response”する学生もいれば,何を聞いていたのか“shift response”ならぬ“indifferent response”する学生もいます。こんなことは講義で言っていないのにという質問もあります。COVID-19以前は,講義の最後に紙で質問票を提出させていたのに対して,COVID-19以降は,PandAの課題として提出させるようにしました。そうすると講義に出席していなくても質問票を提出できるので,このような質問が出てくるのだと推察しています。
学生は意識していないと思いますが,気持ちよく講義させてくれるときと,学生が講義に集中していないことが気になって,うまく話できないときがあります。その点オンライン講義のときは,学生の顔が見えず,何をしているのかわからないので,話に集中することができました。学生に対しては,「講義を受ける君たちの態度で,講義の質は決まる。教員をのせればよい講義となり,もっと多くのことを学ぶことができる。」と言ってはいますが,これもうまく伝わっているかどうかわかりません。質問を見ていると,これを理解している学生もいれば,いまだにしょうもない質問を書いてくる学生もいます。学生にとっては,90分間ずっと集中して話を聞くことは不可能であり,聞いていない時もあるはずです。自分でも90分間一言も漏らさず聞き取り,記憶できるか,と問われれば,そんなことは不可能だと答えるしかありません。ローレン・B・ベルカー,ジム・マコーミック,ゲイリー・S・トプチック著「マネージャーの全仕事 いつの時代も変わらない「人の上に立つ人」の常識」という本によると,話す速度は毎分300字程度であるのに対して,聞く方はこの10倍くらいの情報処理能力があるので,どうしても他のことに関心が移ってしまう,とのことです。学生が携帯電話でSNSをチェックしたりしてしまうのは,先生の話す速度が遅いからということになります。これは人の話に集中していない自分への言い訳にも使っています。
質問に対する回答を書く際,講義で説明したのに,と少々腹を立てながら「講義で説明したように」,「前回の質問票にも解答したように」というような枕詞を多用し,時に学生が恐怖心を抱くこともあったようです。そこで,自らを落ち着かせるため,一度回答を打ち込んだ後,少し時間をおいて,再度落ち着いて最初から見直すことにしました。そうすると,きつく書きすぎたことに気づき,低めのトーンにするようになりました。
「質問と回答による対話」では,学生と意思疎通できているように思っていましたが,大学での講義を終えるにあたり,学生との付き合い方は難しいものだとあらためて思います。1月20日の講義に対する質問票への回答が最後になります。「講義で説明したように」という枕詞は使わないようにしようと思っています。
(建築学専攻 2025年3月退職)