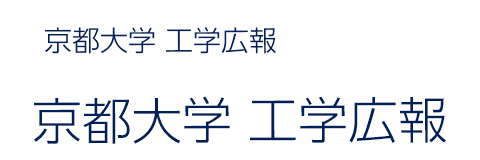「アルゴリズムが支配する世界」か「人生万事塞翁が馬」か?
名誉教授 川上養一

大阪大学の工学部・電気工学科,工学研究科・電気工学専攻で学部,修士,博士と計9年間過ごし,平成元年から京都大学に赴任してから現在に至るまで,本学に身を置いてきた。私の研究分野は,ワイドギャップ半導体の光物性に関するものであり,このテーマに修士課程で巡り合って以来,魅せられ続けて40年間を経て現在に至っている。その端緒は,苦労して作製したちっぽけではあるが宝石のように貴重な半導体結晶を,液体ヘリウム入りのガラスデュワーに取り付けて,暗室下で紫外レーザを照射したときに発生する青色の蛍光を観測し,その美しさに見入ったという感動からスタートしている。そして,その青色蛍光を分光測定した発光スペクトルの起源が,半導体中に形成された電子(マイナスの電荷をもつ)と正孔(電子の抜けた穴に相当しプラスの電荷をもつ)がクーロン力によって引き合った励起子というペア状態が数nmという微小領域で形成され,そのあと10億分の一秒という時間スケールで再結合することでフォトンが発生したものであると学んだことが,固体物理の不思議と素敵に魅了された要因となっている。とはいえ学生時代に将来大学の教員になるなどと夢にも思っていなかった。ただ,指導教員や研究室の先輩からは,この青色発光を室温で電流注入によって高効率に発生させること(すなわち青色発光ダイオード(light emitting diode, LED)の実現)ができれば,確実にノーベル賞をもらえる成果になるとの励ましも,志を大きく持つという点で大きかったのかもしれない。その後,2014年には,「高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色LEDの発明」に関する成果に対して,赤﨑勇,天野浩,中村修二の各教授へのノーベル物理学賞が授与され,上記予想は現実のものとなった。このビックニュースは,自分が直接関与できなかった悔しさはあるものの,長年この分野にかかわってきた一研究者として,日本人として,大変誇らしく思っている。このあたりの研究の背景については,すでに解説書に報告済みであるが,ここではその中から本題にかかわるエッセンスを紹介し,所感に繋げ記しておきたい。
LEDの発光原理を簡単に説明しておこう。半導体に適当な不純物をドーピング(添加)すると,絶縁性から電気伝導性に性質が変化する。この電気の流れを担う担体として,電子と正孔があり,前者がn型半導体,後者がp型半導体によって実現する。これら両者を重ね合わせたpn接合に順方向に電圧を加えると,接合界面において電子と正孔が出会って対消滅するが,その際に生じるエネルギーを光子に変換させることで発光が生じる。LEDの発光色は,両者のエネルギー差である禁制帯幅(バンドギャップ)によって決定される。したがって,可視域でも短波長域に位置する青色発光の実現には,GaN(窒化ガリウム)のようなワイドギャップ半導体が候補となるが,ブレイクスルーにはいくつかの常識への挑戦があった。ここではそのうちの一つに絞って述べておく。それは,40年前当時は,GaNの不純物ドーピングによる電気伝導度制御が困難であり,とりわけp型電導度制御は実現していなかった点にある。そのような当時の現状を受けて,研究者たちは,二通りの考え方をした。すなわち,どんなに頑張ってもp型電導度制御は不可能と考える人たち(悲観派)と,何とか方策を見つければp型電導度制御は可能と考える人たち(楽観派)である。悲観派の根拠となったのは,自己補償効果である。この効果は,p型化のために異種原子をドーピングして正孔を作ろうとしても,その異種原子のまわりで原子空孔(原子の抜けた穴)や格子間原子が発生してこれらによって生成した電子が正孔を補償してしまうというモデルであり,熱平衡状態ではエネルギー安定化の観点から絶対不可避の現象と捉えていたためである。実際そのことを裏付けるような論文が,フィジカルレビューという権威ある学術誌に掲載されていたことも大きく,勉強好きの人たち(物知り博士)は,この呪縛から離れられなかったと言える。一方で,楽観派は,非熱平衡下で結晶成長を行い欠陥濃度や意図せぬ不純物の混入を低減すればp型化が実現可能と信じ取り組んできた実験屋さんたちであり,2014年のノーベル物理学賞は,まさしくその実験屋さんたちによる成果なのである。
さて,近年は莫大な実験結果や論文データの解析ができるようになり,デジタル技術に立脚した機械学習,AIなどの情報科学を用いて新規材料探索,半導体プロセス開発やデバイス設計の高効率化が行われるようになってきた。これは,開発への投資に対して最大限のリターンを期待するコスパ重視の観点から必然の流れであり,私もその有効性と将来性はもちろん肯定する立場にある。しかしながら,上記ブレイクスルーは,そのような情報科学からのみでは成しえなかったものであることは明記しておきたい。人間ができる素晴らしい能力は,先人の偉業を深く勉強するだけではなく,教科書に書かれていることであってもそれを疑って自分なりの仮説を立て,それを検証するという姿勢であり,たとえそれが失敗しても,その失敗を糧として前を向いて行くという生き方こそが大切なのである。ユヴァル・ノア・ハラリが著した「21 Lessons——21世紀の人類のための21の思考」によれば,これから数十年後には,ビックデータとAI技術の進歩により大きな変革が訪れることは疑いようがなく,とくにバイオ・医療・ITがこれまでの権威や自由主義を破壊し,アルゴリズムが支配する世の中になるとのことである。いくつかを挙げれば,「医療検査データのみで最適な投薬や治療選択がなされ医者の役割は大幅に縮小する」,「効率性や公正性(過去の判例を正確に分析)からAI裁判官が登場する」などがあげられる。私は,このようなアルゴリズムが支配する世の中は,コスパ至上主義とも言え,便利で有難い一方で,必ずしも人間が幸せにならない側面もあるのではないかと考える。たとえば,マッチングアプリにだけ頼って男女の出会いがあるのではなくて,「男はつらいよ」の寅さんのように振られるとわかっていても,動かし難い情熱と人との出会いを呼び込む勇気こそが,AIやコスパとは対極にあるものであると感じている。光の不思議と素敵に魅了されてきた私の人生は,「人生万事塞翁が馬」や「セレンディピティー」という言葉に触発されてきた。
私は令和6年度末に早期退職し,民間企業に再就職し研究開発を任せられる予定である。この小文は,私たちがどのような未来を志向すべきかを考える機会となればと考え執筆したが,図らずも第二の人生に進もうとしている自分を鼓舞するものともなった。我々の将来に幸多かれと祈念して筆をおく。
(電子工学専攻 2025年3月退職)