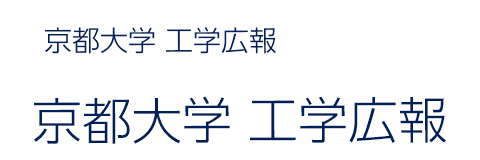学者へのあこがれと出会い
名誉教授 田中 功

定年退職を迎えるにあたり,「工学広報」に寄稿する機会を得た。これまで人生を振り返ることは少なかった。自慢話のような調子で書くことには抵抗がある。しかし,自分もいよいよ定年を迎える年齢となり,学生時代から38年間を過ごした京都大学での歩みを振り返ることは,関わってくださった多くの方々への感謝を表すことになると考え,筆を執ることにした。
大学に入学したのは昭和53年。親元を離れた解放感と,先の見えない意欲に満ちていた。ワンダーフォーゲル部に入り,講義をさぼって山歩きに行き,下山後はヒッチハイクで放浪し,見知らぬ土地の駅舎を借りて寝袋で眠る。講義に出るときは,時間割を無視して,気の向くままに顔をだす。体系的な学習には程遠いものだったが,山歩きの時間を含め,仲間との語らいや本の乱読に多くの時間を費やした珠玉の3年間であった。
4回生で配属されたのは高村仁一教授が主宰されている研究室であった。与えられたテーマは,希薄Au合金における原子空孔と溶質原子との相互作用を液体窒素中での電気抵抗測定に基づいて調べるというものであった。実験は,まずリヤカーに容器を積んで北部構内まで液体窒素を汲みに行くことから始まる。実験をいったん開始すると,2~3日は休まず続ける。極めて時間効率の悪いものであったが,若い自分には,祭りのように愉しい時間だった。しかし,この実験には職人的スキルが求められ,自分の不器用さを痛感することになった。与えられたテーマの範囲で,少し違う内容で卒業論文を書きたいと願うようになった。図書室に籠り教科書や論文を乱読するなかで,原子空孔や溶質原子の電気抵抗への寄与を理論計算できる方法があることを知り,それに没頭した。当時の金属系にあった計算機端末室でプログラムをカードにパンチし,それを大型計算機センターの窓口に提出する繰り返しである。香りと記憶は結びつきやすいと言われるが,当時を振り返ると,地下書庫や端末室の埃,黴,油の混ざった独特の匂いを思い出す。卒業研究で得た最大の収穫は,自ら問題を設定し,教科書や論文を読むことで深く理解する喜びを知ったことである。さらに,計算機を用いて結果を定量化することの爽快さを味わった。この経験を通じて,先人の偉業に感服するばかりでなく,自分もその一端を担いたいという憧れを抱くようになった。
修士課程でも研究テーマは続けることになったが,電気抵抗として測定しているものが,本当に原子空孔や溶質原子に対応しているのか,それを全く別の方法で検証したいと考えるようになった。研究室では,白井泰治博士が陽電子寿命測定により,原子空孔の濃度や形状を測定することを開始しておられた。その議論に参加させてもらうとともに,溶質原子の側からの情報を得るためのメスバウア分光実験を,大阪大学の那須三郎博士のもとに押しかけて実施させてもらうことになった。
修士課程修了後も研究を続けたいという希望があったが,高村教授がちょうど定年退官であったため,大阪大学基礎工学研究科物性物理専攻の藤田英一教授のもとで博士後期課程に進学させていただいた。那須三郎博士が在籍されていた研究室である。この専攻は,物性物理の分野で理論と実験の学者が切磋琢磨しておられるところで,金属分野の工学的な知識しか持ち合わせのなかった自分は,強いカルチャーショックを受けた。新しい実験装置の立ち上げに苦労したことに加え,合間に頑張って勉強しなければ研究室の仲間について行くことも大変だった。とても忙しかったが,のちの研究で使うことになる電子顕微鏡や電子状態計算にも触れさせてもらったこと,海外での国際会議で発表させてもらったことなども含め,人生の大きな節目となった3年間だった。
博士課程を修了して職を得たのは,同じ大阪大学でもキャンパスが異なる産業科学研究所(産研)であり,研究テーマ・環境ともに大きく変わった。研究対象は,当時ブームであった高温構造用セラミックス材料。熱間等方加圧(HIP)装置を利用して,高純度窒化ケイ素粉末を焼結させ,微細構造や力学特性を調べるというものであった。民間企業や外国人の研究者も多く滞在するプロフェッショナルな環境で,それまでの学生気分は吹き飛んだ。ここでも大型実験装置の操作に習熟するだけでなく,セラミックスや固体化学の勉強が必要になり,先人の偉業に押しつぶされそうに感じながらの毎日であった。しかし5年間のこの研究所での滞在期間中に,当該分野の学術や技術の習得だけではなく,国内外の様々な研究者と知己を得たことが,その後の大きな財産となった。
海外に出て自分の力を試したいという思いは学生時代からあったが,産研で海外からの研究者と交流するなかで,その思いが高まった。幸いドイツのStuttgartにあるMax Planck金属研究所のManfred Rühle教授に受け入れて頂き,家族とともに渡独することになった。この研究室は世界の研究者のハブのような役割をしており,著名な学者がサバティカルで滞在していた。これらの先生方は若手との議論にも頻繁に応じてくれ,学ぶことがとても多かった。コーヒーを片手にホワイトボードや,ときには紙ナプキンの上に数式を書いて議論することの愉しさ,そしてアイデアをピンポンのように投げ合う快感は,全てこの時に知ったものである。ドイツでの自分の研究は,日本から持参した高純度の窒化ケイ素セラミックスの粒界構造を高分解能電子顕微鏡で観察するというものであった。そのテーマがちょうど,国際的に注目されはじめた時期で,自分の撮った電子顕微鏡写真をもとに,国際会議で議論が進むといった幸運に恵まれた。さらに,この研究室には電子顕微鏡で分光分析をするグループや,電子状態計算を専門にするグループがあり,そこに潜り込ませてもらって分光や計算の手ほどきを受けたことも,次の仕事の展開に大きく役立った。
ドイツ留学に出るときは,しばらく日本には帰らないつもりであった。しかし結果として,1年の滞在ののちに帰国することになった。京都大学に着任された足立裕彦教授が,研究室の助手にと熱心にお誘いくださった結果である。足立先生は,DV-Xα法という電子状態計算コードを開発し,金属や無機化合物を対象とした研究を精力的に進められていた。私自身は博士課程のときに足立先生に出会い,産研時代にはこのコードを利用してセラミックスの固溶元素についての研究をさせていただいた。それだけの関係であり,電子論の基礎知識も乏しい実験屋にすぎなかったが,足立先生の理論計算グループに参加させていただくご縁をいただいた。京都大学に9年ぶりに戻り,まず驚いたのは学生たちの能力の高さであった。「自重自敬」の伝統の中,彼らは楽しみながら勉強や研究に打ち込んでいた。さらに,その多くが大学院博士課程に進学するという,教員にとっては理想的な環境であった。彼らのおかげで,私の研究も大きく進展した。これもまた大きな幸運と言えるだろう。
研究は,足立先生の理論計算のほかに,ドイツで学んだ電子顕微鏡技術や電子線エネルギー損失分光,放射光を使ったX線吸収分光の実験とその理論計算を進めた。また,産研時代に習得したセラミックス合成実験を統合することで,研究の幅を広げた。着任当初は計算機の台数が限られ,処理速度も遅かったため,計算結果を一つずつ吟味し,学生たちと議論することができた。この時間は,計算科学の初心者であった自分にとって,極めて有益であった。40歳を過ぎた頃から,大型の研究予算に採択いただく機会に恵まれ,計算機や実験装置も充実していったが,その一方で,自ら研究に没頭する時間が減少していくことに忸怩たる思いを抱いた。しかし,確保した予算により,国内外から優秀なポスドク研究者を迎えることができたことは大きな成果であった。44歳で教授に昇任した研究室は国際色豊かであり,多くの海外からの来訪者を迎える中,小さな研究ハブとしての機能を果たせたと感じている。54歳のときには,科学研究費新学術領域研究「ナノ構造情報」の領域代表として採択いただき,情報科学者との本格的な交流が始まった。いわゆるマテリアルズインフォマティクスの黎明期であり,物性理論計算の第一人者である寺倉清之先生から直接ご指導いただく幸運にも恵まれた。
このように振り返ると,私の研究人生は,学者への憧れと幸運な出会いに満ちていたことが分かる。これらの経験は,一つのピースも欠けることのできない貴重なものである。それぞれの出会いに深く感謝し,この文章を結ぶことにする。
(材料工学専攻 2025年3月退職)