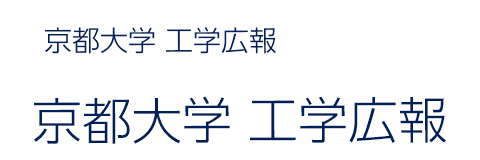アルカリ水溶液系の電気化学
株式会社豊田自動織機 岡西岳太
 私は,1998年に京都大学工学部工業化学科に入学し,2002年に江口研究室(物質エネルギー化学専攻触媒設計工学分野)に配属された。2002年に江口浩一教授が九州大学から京都大学に転任された最初の4年生が,私を含む5名であった。個性が強く,自由奔放な5名の学生を目の当たりにした江口先生は,当時頭を悩ませたに違いない。研究室では,自分で考えて進めるべきという江口先生の方針もあり,自由に研究をさせてもらえた。最初の研究テーマは,メタン改質ガス中のCO除去を目的としたシフト反応触媒であったが,次第に燃料電池自体に興味を覚え,大学院からアノード電極触媒の研究を進めた。当時は,水溶液系の電気化学のノウハウが無かった為,サイクリックボルタモグラムの取得さえままならなかったが,所謂“ビーカーセル”との最初の出会いであった。
私は,1998年に京都大学工学部工業化学科に入学し,2002年に江口研究室(物質エネルギー化学専攻触媒設計工学分野)に配属された。2002年に江口浩一教授が九州大学から京都大学に転任された最初の4年生が,私を含む5名であった。個性が強く,自由奔放な5名の学生を目の当たりにした江口先生は,当時頭を悩ませたに違いない。研究室では,自分で考えて進めるべきという江口先生の方針もあり,自由に研究をさせてもらえた。最初の研究テーマは,メタン改質ガス中のCO除去を目的としたシフト反応触媒であったが,次第に燃料電池自体に興味を覚え,大学院からアノード電極触媒の研究を進めた。当時は,水溶液系の電気化学のノウハウが無かった為,サイクリックボルタモグラムの取得さえままならなかったが,所謂“ビーカーセル”との最初の出会いであった。
修士課程修了後,松下電器産業(現:パナソニック)に就職し,固体高分子形燃料電池(PEFC)の電極開発に従事した。2009年の世界初の家庭用FCエネファームの市場導入に立ち会えたことは貴重な経験であった。社会人としての基礎を叩き込んで頂いたことにも感謝している。また,幸運なことに,2010年に,パナソニックの共同研究先である山梨大学の社会人博士課程に入学し,恩師(内田誠教授,渡辺政廣教授ら)のバックアップもあり,PEFCの電解質膜の劣化メカニズムに関する研究で,無事修了することができた。
自由奔放な私は,2013年に,パナソニックを飛び出し,江口研究室に特任助教として雇って頂いた。ここでは,アンモニアやアルコールの酸化反応など,“ビーカーセル”を用いてアルカリ水溶液系の電気化学に注力した。その後,縁あって2016年に,豊田自動織機に入社し,ハイブリッド自動車向けニッケル水素電池の開発を担当した。開発当初は,電池の形さえ無い状態で,“ビーカーセル”を駆使し,電極材料,電解液の開発に没頭した。京都大学で培ったアルカリ水溶液系の電気化学の知見は大いに活きた。後発電池メーカーとしてのビハインドを打破すべく,2021年に自動車向けとしては世界初のバイポーラ型ニッケル水素電池の量産化にこぎつけ,トヨタ自動車のアクアに採用された。お陰様で,その後,搭載車種も増え,クラウン,RX,アルファード,ヴェルファイアなどに採用されるに至っている。近年は,ライフワークになりつつあるアルカリ水溶液系の電気化学とニッケル水素電池の開発で培った知見を元に,アルカリ水電解用貴金属フリー電極を新たに開発した。ニッケル水素電池と同様,量産化までやり切る所存である。
思い返せば,自由に動く中でも,触媒化学,電気化学という軸を残していたことが,今に繋がっており,何より学生時代,特任助教時代に自由に研究をさせていただいた江口先生始め,関係者の皆様には感謝してもしきれない。今後,何らかの形で大学に恩返しさせて頂きたいと考えており,本稿がそのきっかけになれば幸いである。
(物質エネルギー化学専攻 2004年3月修士課程修了)