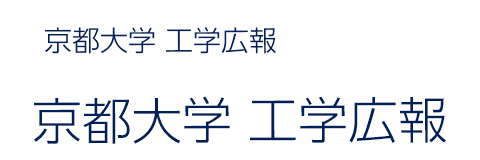基礎から技術の進展を担う
助教 西岡季穂

私は2018年に大阪大学基礎工学部化学応用科学科を卒業後,2022年9月に同大学の大学院基礎工学研究科物質創成専攻で博士(理学)の学位を取得し,2023年3月に京都大学大学院工学研究科材料工学専攻の助教として着任しました。専門は電気化学です。高校生の頃に大学では「化学」を専攻したいと考え,化学応用科学科に進学しました。当時の私にとって化学というと,ビーカーをふって有機分子を合成するというイメージでした。しかし,大学の講義で本格的に学んだ「物理化学」という学問領域の魅力に惹かれて,研究室配属時にはその一分野である電気化学を専門とする研究室を選びました。
研究室配属後は,社会の役に立つ研究がしたいと考えて,リチウム空気二次電池という次世代の二次電池の研究に取り組みました。ただし,私がこれまで実際に取り組んできたのは,「電池をつくる研究」というよりも,その前段階にあたる基礎研究です。リチウム空気電池は,空気中の酸素を反応に利用することから,極めて軽く理論重量エネルギー密度が非常に大きいことが特徴です。故に『究極の次世代二次電池』と称されており,電気自動車や大型ドローンなどへの実装が期待されています。しかし,こうした期待とは裏腹に,現在の技術レベルでは20回程度の充放電しか行うことができず,実用には至っていません。現在の技術レベルを実用段階にまで引き上げるためには,ブレークスルーが必要です。
そこで,確固たる科学的知見に基づいた理解こそが突破口になると考え,電池内で起こっている化学反応の機構を明らかにすることを目的にこれまで研究を進めてきました。研究をはじめた当初は,所属研究室内でも二次電池に関する研究の経験があまりなかったこともあって,試行錯誤の連続でした。特に,電池内では様々な化学反応が同時に進行するため,その個別の反応を適切な方法で切り分けて,分析することが難しいことが課題としてよく挙がります。今も,少しずつ困難を克服しながら小さな発見を積み重ねていくことで,電池内で起こっている現象の詳細な理解を深めている途中です。ただ,着実に研究は前進しており,その事実にやりがいを感じています。
京都大学に着任して以降は,新しい環境で新しい刺激を受けながら研究を進めています。物理系の材料工学専攻に所属することで,材料プロセッシングのための電気化学の考え方に触れ,この分野を違う角度から見つめ直すことができました。
私は,基礎から技術の進展の一端を担える研究者でありたいと考えています。そのために,研究対象については視野を広げつつも,これからも応用・実用化に向けた基礎的理解を大事にした研究を進めていく所存です。
(材料工学専攻)